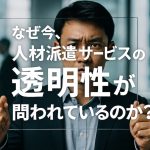最終更新日 2025年7月7日
古式ゆかしい雰囲気のある神社は、御朱印集めや神社婚がブームになってからさらに注目が高まっています。
仏教のように開祖を持たないため森や山、木や人、動物などありとあらゆるものが神に崇められており、神道の世界では八百万の神々と言われるほどです。
現在日本には大小合わせて10万社以上あり、いろいろな物が神として祀られているのがわかります。
その頂点に位置するのが神社本庁と呼ばれる組織です。
目次
天照大神をお祀りしている伊勢神宮
多くの場合その土地にゆかりのある神を祀っていますが、天照大神をお祀りしているのが伊勢神宮です。
そして学問の神様と言われる菅原道真公が祀られているのが太宰府天満宮、世界文化遺産にも登録されている日光東照宮は徳川家康が祀られています。
パワースポットとして有名な平安神宮は桓武天皇と孝明天皇が、宇佐神宮には応神天皇が祀られており、自然物以外にも人や皇室も神となっています。
意外と知られていないのが京都府の伏見稲荷神社のお稲荷様です。
このお稲荷様はキツネと勘違いされるのですが、実は眷属と言われる不思議な生き物であり、神の使いとして祀られています。
このように龍など想像の上での動物も縁起が良いと言われおり象徴として大切にされています。
なお神道の場合、神社は神域としてとらえられ、死は穢れであるという考えのため中には墓地は建墓されておらず、葬儀も行われません。
大きな朱色の鳥居をくぐるところから始まる
仕組み的にも大変興味深く、まず大きな朱色の鳥居をくぐるところから始まります。
そのまますっとくぐってしまいがちなのですが、本来鳥居は神域への入り口であるので、くぐる際には頭を下げてお辞儀をするのが基本です。
昔はこの鳥居は木や石でできていたのですが、近年ではコンクリートや樹脂、金属でできているものもあります。
鳥居をくぐると社殿へと続く参道が見えます。
石畳や玉砂利が敷かれており、参道を歩くことによって神社敷地内をめぐることができるようになっています。
この参道はただ歩くだけのスペースではなく神もまた通る道でもあるため、中央部分は歩くことはできません。
そのため左右どちらかに歩くのがマナーです。
参拝をする前に手を洗い口を漱いで身を清める
参道を進んでいくと最後の鳥居の前に手水舎があります。
ここでは参拝をする前に手を洗い口を漱いで身を清めます。
ひしゃくで水を汲んだらまず左手をすすぎ、次に右手をすすぎます。
その後左手で受けた水で口をすすぎ、最後にもう一度左手を清めひしゃくを元に戻します。
難しいように感じますが、左手から始まると覚えておくと比較的楽にできるので、気負う必要はありません。
なお参道を歩いていると森のような空間が現れます。
これは鎮守の杜と呼ばれており、神が降臨して住んでいる神聖な場所と言われています。
この木は切ることができず、さらに枯れ葉であっても持ち出してはいけないとされており、自然そのものを感じることができます。
また鎮守の杜の中にはひときわ目立つ巨樹があり、これがご神木としてあがめられます。
拝殿の両脇に獅子のような狛犬が現れる
ご神木にはしめ縄が締められており、他の木々とは異なる雰囲気です。
このようなことからパワースポットとしても有名になっており、日本だけでなく海外からも多くの人が不思議な力を求めて訪ねてきます。
そのまま進んでいくと拝殿の両脇に獅子のような狛犬が現れます。
守護神であり、よく見ると口を閉じている狛犬と開いている狛犬とがいますが、これは仏教に由来しているものではありません。
また神社によっては狛犬ではなく狼や牛、サルを神の使いとしているところもあります。
訪れた際には、どのような動物が守護聖獣なのかを見ると良いでしょう。
より一層歴史を感じることができます。
拝殿まで来ると実際に参拝をすることが可能です。
二拝二拍手一拝が作法
拝殿前で立って行うのは略式参拝と呼び、多くの場合この略式参拝を行っています。
お賽銭箱にお賽銭を投入し、鈴を鳴らして神をお呼びし礼拝を行いますが、二拝二拍手一拝が作法です。
神道はこの方法が基本なのですが、例外として出雲大社は四拍手、伊勢神宮は八開手、八度拝です。
寺院では手を静かに合わせるだけですが、神道ではしっかりと手を鳴らすので忘れずに行うようにしましょう。
拝殿の奥には本殿があり、この本殿に神が祀られています。
よく見ると本殿の周りに玉垣がされていますが、これは景観のためのものではなく外界とを区切るためのものであり、玉垣の外側が俗界、そして内側が神域となります。
一見すると大変簡素な造りのように感じますが大変複雑であり、どれも木を用いて組み込まれており、建造物としても興味深いものでもあります。
まとめ
シンプルな色合いであるため日本の良さを感じることができるのも魅力の一つであり、凛とした空気を感じることもできます。
地域によって雰囲気が全く異なるため、いろいろな場所を巡ってみても良いですし、住んでいる土地にどのような神が祀られているのかを再確認しても良いでしょう。
古来、人々がどのような思いで神を祀ったのかを思い巡らせることができ、より一層その土地に愛着がわいてきます。
神社本庁に関してよくある質問
Q1: 神社本庁は何ですか?
A1: 神社本庁は、日本の全国的な神社の統治機関のことを指します。
神社本庁は、神社の管理、整備、保全、そして宗教指導などを行うことで、日本の文化や宗教を振興することを目的としています。
Q2: 神社本庁はどこにありますか?
A2: 神社本庁は、東京都千代田区にあります。
具体的には、千代田区永田町にある「神社本庁大社」に本庁があります。
Q3: 神社本庁にはどのような役割がありますか?
A3: 神社本庁には様々な役割があります。
主な役割としては、全国的な神社の管理や整備、宗教指導、文化振興、国民の祈願や参拝を受け付けることなどがあります。
また、神社本庁は、国民の祈願や参拝を受け付けることで、国民の精神的な支援をすることも目的の一つです。